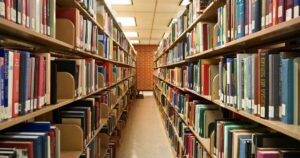【自費出版】図書館に本を置いてもらう方法|献本・寄贈の手順と受け入れられるコツ
はじめに
「自費出版した本を図書館に置いてもらいたい」 「地元の図書館で自分の本を読んでもらえたら嬉しい」
そんな想いを持つ自費出版者の方は少なくありません。しかし、実際には「どこに送ればいいの?」「断られることはある?」「ISBNって必要?」など、わからないことだらけではないでしょうか。
この記事では、初めて自費出版を行う方に向けて、国立国会図書館への納本と地域の公共図書館への寄贈の両方について、具体的な手順から受け入れられやすい本の特徴、そして注意すべきポイントまで徹底解説します。
図書館に本を置いてもらう2つの方法
自費出版物を図書館に置いてもらう方法は、大きく分けて2つあります。
1. 国立国会図書館への納本(法的義務)
国立国会図書館への納本は、国立国会図書館法に基づく義務です。一定の条件を満たす出版物は、必ず納本しなければなりません。
2. 公共・地域図書館への寄贈(任意)
地域の公共図書館や学校図書館への寄贈は任意です。受け入れるかどうかは各図書館の判断に委ねられています。
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
国立国会図書館への納本(義務)
納本制度とは?
国立国会図書館への納本は、現在と未来の読者のために、国民共有の文化的資産として永く保存することを目的とした制度です。
重要: これは「特典」ではなく「義務」です。
納本の対象となる自費出版物
以下の出版物は納本対象となります:
- 一般書籍、雑誌、新聞
- 小冊子、楽譜、地図
- CD-ROM、DVDなどのパッケージ系電子出版物
- 個人出版の私家本や同人誌
- ISBNが付与された図書
納本義務の基準: 頒布目的で相当部数が作成された出版物が対象で、自費出版物は100部程度が基準とされています。
国立国会図書館への納本についてはこちらの記事で詳細をまとめていますのでご覧ください。
【2025年版】自費出版後の国会図書館納本は必要?手続き方法と代償金申請を完全解説 | MAP出版株式会社
公共・地域図書館への寄贈(任意)
地域の公共図書館や学校図書館への寄贈は任意ですが、受け入れられるかどうかは完全に各図書館の判断と方針次第です。
寄贈の基本的な流れ
STEP1: ISBNコードの取得(重要)
図書館に置いてもらうには、ISBNコード(国際標準図書番号)と日本図書コードの付与がほぼ必須です。
- これらがない場合、受け付けない図書館が多い
- 出版社が代行する場合もあるが、個人でも取得可能
- 日本図書コード管理センターへの申請(約2週間)
(参考)自費出版のISBN取得完全ガイド|費用・手順・注意点を徹底解説」 | MAP出版株式会社
STEP2: 寄贈先の図書館を選定
以下を基準に図書館を選びます:
- 書籍に関連する地域の図書館
- 自分が過ごしたゆかりのある学校
- 内容に関係性のある図書館
STEP3: 寄贈ガイドラインの確認
必ず事前に確認: 各図書館のウェブサイトで「寄贈のガイドライン」や「寄贈受付の有無」をチェックしてください。
ガイドラインがない場合は、電話で事前相談するとスムーズです。
STEP4: 送付状の作成
書籍を送る際は、必ず適切な送付状を作成し同封します。
送付状に書くべき内容:
- 作品への想い
- なぜその図書館へ送りたいのかという関連性
関連性を明確に伝えることで、受け入れられる可能性が高まります。
STEP5: 送付または持参
送付方法:
- 直接カウンターに持ち込む
- 郵送で送る
持ち込み方法は各図書館に確認をしてください。
重要な注意点:
- 送料は必ず自己負担(元払い)。着払いは厳禁
- 自宅等への引き取りは行われない図書館が多い
STEP6: 結果を待つ
寄贈後の確認や問い合わせは控えましょう。図書館側の判断を尊重することが大切です。
受け入れられやすい本、断られやすい本
図書館はスペースが限られているため、すべての寄贈本を受け入れられるわけではありません。図書館の資料収集方針に適合するかどうかが判断基準となります。
受け入れられやすいジャンル
1. 地域資料・郷土資料
地域性の高い内容の書籍は歓迎されます:
- 地元をテーマにした童話
- 地域を研究した歴史関連書籍
- 地域の文化や風習を記録したもの
事例: 市川市のように、市民の著作物(自費出版含む)を「市民文庫」として積極的に収集している図書館もあります。
2. 公共性の高いテーマ
社会問題や環境問題など、公共性の高いテーマの本は並べられやすい傾向があります。
3. 入手困難な資料
一般の流通ルートにのらない貴重な資料は評価されます。
4. 体裁・品質が高いもの
表紙や装丁、印刷品質が商業出版と遜色ないレベルであることが重要です。
原則として受け付けられない資料
多くの図書館で、以下の自費出版物は受け入れが難しいとされています:
私的な色彩が濃いもの
- 自分史
- 家系に関する著作
- 各分野の随筆
- 非専門家の調査研究・報告書
特定の文学作品
- 小説・詩・俳句・短歌等の文学作品
コレクション
- 写真集
- 絵画集等の作品集
特定の思想・営業目的
- 政治・宗教の布教を目的とした内容
- 特定企業の営業目的の内容
- 一般的でない偏った思想のもの
品質が低いもの
- カビやシミなどの汚れがひどいもの
- 壊れているもの
- 書き込みがあるもの
流通性に問題があるもの
- 出版年の古い実用書・ガイドブック
- 百科事典
- 図書館で継続購入していない雑誌
地域図書館以外の寄贈先
地域の図書館で断られた場合でも、専門的な施設なら受け入れてくれる可能性があります。
専門図書館・施設
日本現代詩歌文学館
詩・短歌・俳句などの作品集の寄贈を受け付けています。
自分史専門施設
日本自分史センター(愛知県春日井市)など、自分史作品の寄贈を積極的に受け付けている施設があります。
自分史のような私的な色彩の濃い本は、地域図書館では断られることがあるため、こうした専門施設への寄贈を検討しましょう。
福祉・教育施設
子ども向けの絵本や童話は、以下への寄贈が喜ばれます:
- 幼稚園
- 福祉施設
- 介護施設
- 児童養護施設
事前連絡を忘れずに: 必ず事前に連絡して、受け入れ可能か確認しましょう。
寄贈・納本する際の重要な注意点
1. 寄贈後の取り扱いは図書館に一任される
寄贈を受け付けた資料が図書館の蔵書として受け入れられるかどうかは、すべて図書館側の判断です。
覚悟すべきこと:
- 個別の連絡はない(受入れの可否や返却等の問い合わせには応じられない)
- リサイクルコーナーで他の市民に提供される可能性
- 廃棄処分となる可能性
絶対にしてはいけないこと:
- 置いてもらえないことが分かった後、返却を求める
- 受け入れ状況の確認を強要する
図書館側の判断を尊重し、潔く受け入れる姿勢が大切です。
2. 出版社の献本代行サービスを活用
自費出版サービスを提供する会社の中には、図書館への配本や納本をサポートするオプションがあります。
献本代行サービス:
- 出版社が図書館への献本(寄贈)を代行
- 料金例: 1件1,000円+税
営業・広報活動:
- FAXでのお知らせやDM送付
- 注文用チラシの作成とFAX送信(全国の図書館に購入を促す)
3. 「図書館マーケティング」という戦略
在庫処分や広報手段として、全国の図書館へ寄贈する「図書館マーケティング」という手法があります。
目的: 買い取った大量の在庫を処理しつつ、多くの人に読んでもらう機会を増やす
実際の効果:
- 「図書館の本で知りました」という注文が少数ながら入る実績あり
- 在庫として眠らせておくよりは有意義
成功の2つの条件:
- 商業出版と遜色ない高い体裁
- 社会問題など公共性の高いテーマ
実施のタイミング: 本は出版日が古くなるほど価値が下がるため、早いほうが良いとされています。
まとめ: 図書館に本を届けるために大切なこと
自費出版した本を図書館に置いてもらうには、以下のポイントを押さえましょう。
国立国会図書館への納本:
- 100部以上発行した場合は納本義務がある
- 無償納入なら1冊から簡単に寄贈できる
- 発行後1ヶ月以内に送付(送料自己負担)
公共図書館への寄贈:
- ISBNコードの取得がほぼ必須
- 地域性や公共性の高いテーマが受け入れられやすい
- 事前にガイドラインを確認
- 受け入れられない可能性を受け入れる覚悟が必要
品質へのこだわり:
- 商業出版と遜色ない体裁
- 乱丁・落丁のない完全本
- 地域や社会に貢献する内容
あなたの想いが込められた本が、図書館を通じて多くの人に届くことを願っています。
自費出版をお考えの方へ
「図書館に置いてもらえる本を作りたい」 「ISBNコードの取得から献本まで、すべてサポートしてほしい」 「どんな内容なら受け入れられやすいか相談したい」
そんな方は、ぜひMAP出版にご相談ください。
MAP出版では、企画から編集、装丁デザイン、ISBNコード取得、印刷、そして国立国会図書館への納本や販促まで、自費出版に関するすべてのプロセスを丁寧にサポートいたします。
図書館に受け入れられやすい本作りのノウハウも豊富です。初めての方でも安心して出版できるよう、経験豊富なスタッフが一冊一冊、心を込めてお手伝いします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
▶ MAP出版に相談する
この記事の情報は2025年10月時点のものです。各図書館の方針は変更される場合がありますので、最新情報は各図書館の公式サイトでご確認ください。